 陰陽の対立図式当てはめて、物の起こりし謂れ究めや
陰陽の対立図式当てはめて、物の起こりし謂れ究めや
7inyou.htm
7inyou.htm
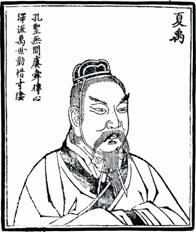
本日は陰陽五行説を解説しておこうと思います。陰陽説は伏羲が始め、五行説は夏の創始者「禹」が発案したものとされています。
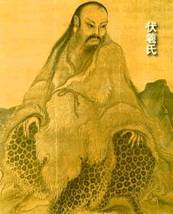 陰陽説と五行説総合したのが、戦国時代の陰陽家鄒衍です。鄒衍により5つの惑星と、さらにその後様々な事象と結び付けられ、陰陽思想と五行説が統合されて観念的な陰陽五行思想として完成したのです。
陰陽説と五行説総合したのが、戦国時代の陰陽家鄒衍です。鄒衍により5つの惑星と、さらにその後様々な事象と結び付けられ、陰陽思想と五行説が統合されて観念的な陰陽五行思想として完成したのです。
現在ではそれらがどのように説かれたのかははっきりわかりません。鄒衍の著作も残存していないようです。だから陰陽五行説の歴史的発展を跡付けることはできませんが、これが中国人の世界観のようになっており、儒家や道家および道教の区別なく、すべて陰陽五行説で解釈され、説明されますので、一応理解しておく必要があります。
 陰陽五行説は易に由来しており、呪いや占いの原理になっています。それで非合理的なものに見えるかもしれませんが、西洋科学を信じているので、そう見えるわけで、陰陽五行の論理自体は合理的科学的な自然や人間、社会についての捉え方とみなされているわけです。
陰陽五行説は易に由来しており、呪いや占いの原理になっています。それで非合理的なものに見えるかもしれませんが、西洋科学を信じているので、そう見えるわけで、陰陽五行の論理自体は合理的科学的な自然や人間、社会についての捉え方とみなされているわけです。
物事を対照的、対極的な二つの言葉に分類するとすれば、それは何かということですが、光が強い「明るい」と光が弱い「暗い」という言葉、言い換えれば「陽」と「陰」に分類したわけです。つまり「陽」の箱(範疇つまりカテゴリー)に入る概念と「陰」の箱に入る概念を並べて対照表にしたわけです。
|
陽 |
天 |
男 |
太陽 |
昼 |
夏 |
南 |
気 |
背 |
腑 |
剛 |
奇数 |
|
陰 |
地 |
女 |
月 |
夜 |
冬 |
北 |
血 |
腹 |
臓 |
柔 |
偶数 |
この表でだいたい納得いきますが、体に関するものは医学に素人ですので、陽に気・背・腑が入り、陰に血・腹・臓が入るのは何故か分かりにくいですね。まあ乾燥しているのが陽、湿っているのが陰としますと、気が陽、血は陰ですね。それに背は主に背骨でできており、腹は胃腸ですので、背が陽と腹が陰ということでしょうね。表が陽、裏が陰から考えると、腹は陽で、背は陰の筈ですが。
陰陽と陰を先に書きますが、陽の方が貴いとされます。「天は貴く、地は卑しい」とされるのです。ですから支配者は天の子つまり天子を自称します。人民は土に生きるわけで、天子は貴いということですね。
男と女は、男が能動的で、女は受動的だとみなされますので、男が陽、女が陰です。これは性器の形が、男が凸型で、女が凹型で能動、受動を示しています。能動が陽、受動が陰ということでしょう。キリスト教ではセックスの体位で女性上位は禁止されていました。あくまで男が上になってセックスしなければならないということですね。中国ではそういう性道徳はどうなっていたかまでは知りませんが。男尊女卑は徹底しています。
ただし諸子百家でいいますと、儒家は表向きの建前で陽ですが、道家は低きにつくとか受動的な無為を強調しますし、「玄牝の門」とか「谷神は死なず」とか言って女性原理に立っているところがあります。
陽に昼・夏・南で、陰に夜・冬・北というのは納得ですが、ただ、北と南では北の方位に天子が南面して座りますから、陽が貴いという理屈に合わない気もしますね。北極星という天帝も北の方角に居ます。
数字のことで奇数・偶数で、奇数が陽で聖数とされています。縁起がいい数字になっているわけです。ただ陽数が重なりますと陽の気が強すぎるのでかえって、バランスを欠き、不吉とされて、厄払いの祭礼が行われます。最大の奇数の九が重なる九月九日は「重陽の節句」と呼ばれて、特に盛大に祀られます。ところが陽は縁起がいいので、重なった方がいいという捉え方に代わりまして、そのめでたさを祝うようになったということです。
日本では重陽の節句として五節句が行われていますが、いずれも災厄を払う行事ですから、陽気が重なるということはやはりめでたいだけではないようです。
「人日の節句」とは五節句の1番目の節句で、陰暦1月7日です。七草粥を食べて1年の豊作と無病息災を願います。上巳(じょうし)の節句「上巳」は3月3日にあたり、「桃の節句」とも言われます。桃などの自然の生命力をもらうなどして厄災を祓います。「端午の節句」は5月5日にあたり、「菖蒲〔しょうぶ〕の節句」とも言われます。強い香気で厄を祓う菖蒲やよもぎを軒(のき)につるし、また菖蒲湯に入ることで無病息災を願いました。そして7月7日が七夕ですね。これは牽牛と織女の逢瀬を祝う日で、織姫にあやかって機織が上達するように祈る乞巧奠(きこうでん)という行事があります。この時もやはり災厄を避ける薬膳が出されるようです。
陰と陽は相関概念ですから、明るいものは陽ですが、より明るいものに対しては陰になります。元々の太極は混沌であって、そこから全てが生じたわけですから、同じ気(物質)が陰陽に分かれているわけです。このように太極から陰と陽に分かれることを「太極から両儀へ」といいます。
陰陽の両儀は相反する性質をもちますが、互いに往来し、却って互いに引き合って、交感・交合するものなのです。天地の交感、交合というのは太陽の日差しや、星の輝き、雨風など天地の交感・交合によって万物は生成し、成長し、消滅し、輪廻するとされます。
男女の交感・交合は子を生むわけですが、陰陽の原理自体が陰陽の対立・交感・交合から全てが生じ、変化するというものですから、性的原理で世界を捉えようとする性的自然観、あるいは性的世界観といえるかもしれません。そうしますと男女のセックスというのは単に快楽の原理であるのではなく、世界を生む原理だということになります。伏羲・女媧の夫婦神、イザナギ・イザナミの夫婦神はそれを象徴しているわけです。また世界が陰陽という男女両性に分かれ、それが交感・交合して万物・万象が生じているということは、コスモス(宇宙・世界)全体が大いなる生命として捉えられているといえるのかもしれませんね。
さて太極から両儀が生じ、両儀から四象が生じるといいます。漢代には、両儀は天地または陰陽と解されまして、四象は春・夏・秋・冬の四時と解されていたようです。つまり四季の変化は陰気と陽気の相互作用によって生じると考えられたのです。つまり両極が混ざり合って中間的なものが生じるわけですが、そこには変化の方向があるので、冬から夏に至る中間に春が、夏から冬に至る中間に秋が生じるということでしょう。
一方、五行学説では四時の気は木・火・金・水とされていましたので、前漢末になって、五行説が易学に取りこまれていきますと、四象も直接的に五行の木・火・金・水を指すようになったようです。

気に入らぬ卦がでて八卦やり直す
当たるとすれば初
筮にあらずや
易の八卦(はっけ、専門家は「はっか」と読むらしい)を図にしますとこうなります。陽爻 と陰爻下から並べます。陽の上に陽を並べると太陽で、陽の上に陰を並べると少陰です。そして陰の上に陽を並べると少陽で陰を並べると太陰です。陽中にあって、太陽は陽ですが、少陰は陰なのです。また陰中にあって少陽は陽ですが、太陰は陰です。つまり陰陽は相関する相手との関係で陽か陰が決まるのです。
と陰爻下から並べます。陽の上に陽を並べると太陽で、陽の上に陰を並べると少陰です。そして陰の上に陽を並べると少陽で陰を並べると太陰です。陽中にあって、太陽は陽ですが、少陰は陰なのです。また陰中にあって少陽は陽ですが、太陰は陰です。つまり陰陽は相関する相手との関係で陽か陰が決まるのです。
四象に陽爻 と陰爻
と陰爻 を重ねまして三つずつにしますと、八卦になります。太陽に陽を加えますと乾です。太陽に陰を加えますと兌になります。同様にして、少陰は離と震に、少陽は巽と坎になります。そして太陰は艮と坤に別れます。
を重ねまして三つずつにしますと、八卦になります。太陽に陽を加えますと乾です。太陽に陰を加えますと兌になります。同様にして、少陰は離と震に、少陽は巽と坎になります。そして太陰は艮と坤に別れます。
|
八卦 |
卦名 |
和訓 |
自然 |
性情 |
家族 |
身体 |
方位 |
Unicode |
|
 |
乾(ケン) |
いぬい |
天 |
健 |
父 |
首 |
西北 |
U+2630 |
|
 |
坤(コン) |
ひつじさる |
地 |
順 |
母 |
腹 |
西南 |
U+2637 |
|
 |
震(シン) |
- |
雷 |
動 |
長男 |
足 |
東 |
U+2633 |
|
 |
巽(ソン) |
たつみ |
風 |
入 |
長女 |
股 |
東南 |
U+2634 |
|
 |
坎・戡(カン) |
- |
水 |
陥 |
中男 |
耳 |
北 |
U+2635 |
|
 |
離(リ) |
- |
火 |
麗 |
中女 |
目 |
南 |
U+2632 |
|
 |
艮(ゴン) |
うしとら |
山 |
止 |
少男 |
手 |
東北 |
U+2636 |
|
 |
兌(ダ) |
- |
沢 |
悦 |
少女 |
口 |
西 |
U+2631 |
この八卦は小成卦といい、この表のようにいろんな事物を表しているとされます。この八卦の上にもう一つ八卦を乗せまして、それを組み合わせますと、八十四卦ができます。それが次の表です。これを大成卦と呼びます。その名前は次のようになります。それぞれの卦について易経では詳しい説明がありまして、それを参考にして占いなさいということです。一応陰陽を吉凶で言えば陽が吉、陰が凶ですが、だからと言って下も上もオール陽の乾つまり天の卦が出ても、イケイケということではないのです。六爻の下から初、三、五が陽位で、二、四、上は陰位なので、陽位に陽爻が、陰位に陰爻くれば正で、そうならなければ不正とされ、正の場合は吉が多く、不正の場合は教が多いわけです。
そして下卦と上卦の一と四、二と五、三と六は対応の関係にあるので、その場合は陰と陽である方が「正応」で陰と陰、陽と陽なら「不応(敵応)」とされます。もちろん正応なら互いによい影響を与えることになります。また隣合わせの爻が陰陽だと「比」と呼び、助け合う関係にあるとされるのです。だから対応や比をみながらそれぞれの爻に吉凶がつけられるわけです。
それに社会的地位を爻は表しています。初爻は庶民(平社員)、二爻は士(係長)、三爻は大夫(部課長)、四爻は公卿(重役)、五爻は君主(社長)、上爻は隠退した君主または無位の尊者(会長・顧問)です。ですから地位によってどの爻に吉凶が出るかが違うわけですね。だから社長なら大胆に勝負にでるところが、平社員なら自重してもっと実力をつけてからということもありますし、逆の場合もありえます。上司の爻と陰陽がちがって比になっていればやりやすいということもあるわけです。
もし悪い卦が出てしまった場合に、いい卦がでるまでやり直してもいいかといいますと、それは駄目ですね。迷った時に占うのであって、まず究極まで占いに頼らずに自分で決断すべきです。どうしても最後に易占いに頼らなければならなくなって占ってもらうわけです。占いの結果が気に入らないから占いをやり直すのは、最初からこうしたいということが決まっていたからで、それなら占いは決断を鈍らすだけで有害です。ですから「初筮(しょぜい)は告ぐ。再三すれば瀆(けが)る。瀆るれば告げず。」と言われます。
まあ易断につきましてはその根拠である、陰とでるか陽とできるかは全くの偶然ですから、それで吉凶が決まるというのはやはり迷信でしょう。それよりこういう易断に際して用いる陰陽や天地、男女、積極・消極、乾湿などの両極の対立、交合などから物事を捉えたり、それらが相関的で、支え合ったり、反発しあったりして物事が変遷し、流動していることなどを見据えていることから多くを学ぶことが出来ます。
 この身をも包みて貫く理や五行めぐりて相生相克
この身をも包みて貫く理や五行めぐりて相生相克
では五行説に入りましょう。五行説では五つの元素を五行と言いますが、何故「行」という言葉を使うのか疑問ですね。それは本来がどれも気即ち物質の現われ、様相だということで、固定した実体のように捉えないということでしょう。もちろんそうした大自然の循環に自然の一部である動植物や人間の身体も組み込まれていますから、医学的にも陰陽五行説が説明原理になります。
それで木は燃えて火となり、火は燃え尽きて灰つまり土となり、土が金属を産み、金属に水滴が生じます。これを五行相生と言います。金属から水が生じるというより、土から水が生じるといった方が説得力はあるかもしれませんが、五行の循環図にするためには金属から水が生じるとするしかなかったのでしょう。
五行相克は木は土を破って芽を吹き、土から水や養分を吸い上げて育つので木は土に克ちます。そして土は堤防を作って水害を防ぎます。つまり土は水に克つのです。その水は火事の火を消します。水が火に克つということです。そして火で金属は溶かされます。火が金に克つということですね。金属が木に克つというのはどうしてでしょう。これはのこぎりとか斧で木を伐採するからです。
*五行相生.
相剋関係の図
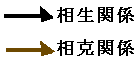
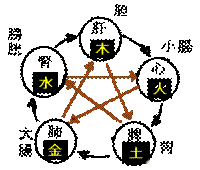
この五行にさまざまな現象を当てはめます、そして木火土金水と同様な相生、相克関係がみられるというように説明するわけです。当然無理な説明になりますね。たとえば金が木に克つように、秋は春に克つといえるか。かなりこじつけの一面的な説明になりかねません。そういうことはあるにしても、五行にさまざな事象を分類して、相生、相克関係を説明することで、世界が合理的にできており、説明可能だという印象を与えることが出来ますね。
**
五行の色体表 **
|
味 |
傷み易い場所 |
声
|
香
|
病症 |
五労 |
刺激 |
色
|
方位 |
季節 |
自然 |
五臓 |
|
酸 |
筋 |
呼 |
|
怒 |
筋 |
風 |
青 |
東 |
春 |
木 |
肝 |
|
苦 |
脈 |
笑 |
焦 |
喜 |
血 |
暑 |
赤 |
南 |
夏 |
火 |
心 |
|
甘 |
肉 |
歌 |
香 |
思 |
肉 |
湿 |
黄 |
中央 |
土用 |
土 |
脾 |
|
辛 |
皮毛 |
哭 |
腥 |
憂 |
気 |
燥 |
白 |
西 |
秋 |
金 |
肺 |
|
齒+成 |
骨 |
呻 |
腐 |
恐 |
骨 |
寒 |
黒 |
北 |
冬 |
水 |
腎 |
|
五行配当表 |
|
五行 |
木 |
火 |
土 |
金 |
水 |
|
季節 |
春 |
夏 |
土用 |
秋 |
冬 |
|
方角 |
東 |
南 |
中央 |
西 |
北 |
|
色彩 |
青 |
赤 |
黄 |
白 |
黒 |
|
時刻 |
朝 |
昼 |
午後 |
夕 |
夜 |
|
臓器 |
肝臓 |
心臓 |
脾臓 |
肺臓 |
腎臓 |
|
五官 |
目 |
舌 |
口 |
鼻 |
耳 |
「怒り過ぐれば肝を傷り、喜び過ぐれば心を傷り、思い過ぐれば脾(胃腸)を傷り、悲しみ過ぐれば肺を傷り、驚き過ぐれば腎を傷る。」(病症)つまり怒りという感情は肝臓と関連しており、喜びは心臓と、思いは胃腸と、憂いは肺臓と、恐れは腎臓と関連しているということです。ですから、逆に肝臓が悪いと怒りっぽくなり、心臓が悪いとよく笑い、胃腸が悪いと思い煩う、腎臓の悪い人はいつもびくびくしていることになります。病気を見立てる場合もそういうことが判断基準になるということですね。
膚や眼瞼に色の変化が現れた時に病気ではないかとよく言われますね。血圧が高いと赤ら顔になり、肺が悪いと皮膚が白くなってしまいます。皮膚や眼瞼の色の変化には注意して、内臓の病気を早期に発見できればいいですね。他にも肝臓の病は青く、胃腸の病は黄色く、腎臓の病は黒くになると言われていますから注意してください。
味覚には酸(すっぱい)、苦(にがい)、甘(あまい)、辛(からい)、鹹(塩からい)の五つの味があります。これを五味といいます。おなじように、五臓とそれぞれ深い関係があります。『素問』に、「肝その味は酸なり、心その味は苦なり、脾その味は甘なり、肺その味は辛なり、腎その味は鹹なり」とあります。つまり、酸っぱいものを食べ過ぎると肝臓を悪くし、苦いものを食べ過ぎると心臓を悪くし、甘いものを食べ過ぎると脾(胃)を悪くし、辛いものを食べ過ぎると肺臓を悪くし、塩からいものを食べ過ぎると腎臓を悪くするおそれがあるのです。
五悪というのは五臓に対して気象が影響を及ぼすことをあらわしたものです。「心は暑を悪み、肺は寒を悪み、肝は風を悪み、脾は湿を悪み、腎は燥を悪む」とあります。
つまり、心臓に問題のある人は暑さを嫌い、また暑さに弱いのです。肺臓に問題のある人は寒さを嫌い、寒さに弱いといわれます。肝臓に問題があれば、風にあたるのを嫌い、風に弱いそうです。脾(胃)に問題がある人は、湿気を嫌い、湿気に弱いようで、腎臓に問題があると乾燥を嫌い、乾燥に弱くなるといわれます。このように五臓と五悪もそれぞれの対応をしているのです。
あるいは他人より寒気がひどくこたえるとき、まず、肺の病かどうかを考えるべきだということですね。もちろん、肺病のときには寒気をできるだけ避けなければならないということですね。
 火の徳はとうに尽きたり黄巾を締めて未来の朝迎えむ
火の徳はとうに尽きたり黄巾を締めて未来の朝迎えむ
鄒衍(すうえん)は、それ以前の各王朝の変遷を、五行説で説明しました。各王朝はそれぞれ別々の五行の徳を持っていると解釈したのです。
五行を帝王に配当するに二法があります。一つは五行相生に由るもので、伏犧氏
(木)・神農氏
(火)・軒轅氏
(土)・金天氏
(金)・高陽氏
(木)・尭氏
(火)・舜
(土)・禹
(金)・商
(水)・周
(木)・漢
(火)とめぐります。
もう一つは五行相勝
(剋)
の順序に由るもので、周の火徳に対して秦は水徳を取り、漢は土徳を取るべしとしたのです。
周は、相克説ですと秦の水徳に負けたので火徳です。相生説ですと商の水徳から生じた木徳
ということになります。秦は、相剋説をとって周の火徳を破った水徳とされました。もし相生説だと火徳からは土徳が生まれるということですね。
秦は短命だったので、漢は周を木徳としたうえで、相生説で、その次の火徳としました。しかし歴史的には帝王一人に一つの徳を割り当てたり、うんと飛ばして相生している場合もありますので、これは易姓革命を合理化するための理屈のような気もしますね。
「赤眉の乱」は紀元後⒙年に起こりましたが、王莽が漢王朝を簒奪して現実離れした政治を行い農民の反乱にあったのです。赤眉軍は敵味方を区別するために漢王朝のシンボルカラー火徳を表す赤色に眉を着色したのです。
二世紀末に「黄巾の乱」が起こりました。
「蒼天已死
黄天當立
歳在甲子
天下大吉」(蒼天已に死す
黄天當に立つべし
歳は甲子に在り
天下大吉)をスローガンにしたのです。ちなみに黄色は五行思想では「土」を表す色で、木火土金水の順に巡るとする法則に合わせれば、「火」(赤色)の王朝である漢の次は「土」(黄色)の王朝だということです。