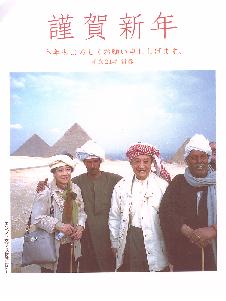
最も多作な思想家の一人が梅原猛である。彼は著作集を二回出している。今の調子で行けば三回目の梅原猛著作集も出そうな勢いである。おそらくそこに収録されるであろう『(仮題)梅原猛最新講演集』を出版しようと、私は五つの講演のテープ起しを担当している。それでも文量が足りないというので、梅原猛はやすいゆたかとの対談をミネルヴァ書房にて、急遽行った。
梅原によれば彼は西田幾多郎の『善の研究』のような独創性があり、普遍的な意義のある哲学書が書けるまでは本は出版しないという決意だったようだ。ところが朝日新聞に連載した「笑いの研究」が評判になり、NHKテレビで『仏像―心とかたち』の総合司会を担当したので、それが本になる際に梅原も書かざるを得なくなった。これが三日で初刷りがなくなってしまい、ベストセラーになった。それから数百冊も本を出版したのである。
でも本格的な哲学書は、まだこれまで独創的な哲学体系が出来上がっていないので、一冊も書いていないという。それがやっと天台本覚思想にエジプトの太陽信仰を取り込んで、西欧の理性や意志中心の哲学をトータルに乗り越える論理を掴みかけてきたので、哲学が書けそうになってきたというのである。どうもヘーゲルの理性主義、ニーチェの意志の哲学を主観性の哲学として批判したハイデッガーの存在の立場を継承して、それを天台本覚思想や太陽信仰(光と熱を根源とする生命、生死する太陽)で濃密にした哲学を樹立しようということのようだ。
性急に書き始めようとすると、死んでしまいそうな気がするそうである。彼は3月20日で84歳になったばかりである。まだ6年間じっくり準備して九十歳を超えてから書き始めるらしい。私はその話を呆然と聞いていて、対談者として応答できなかった。でも心の中では「先生、九十歳を超えてから本格的な哲学書を書くなんてギネスものですよ」と言っていた。だから原稿の段階ではその言葉を入れておいたのである、そうでないと格好がつかない。
確かに思想や哲学に限らないが、物事の根源を問い返すような著作は命を削って書くものである。『地獄の思想』『隠された十字架』『水底の歌』から『法然の哀しみ』と彼は対象と一つになって、その哀しみや怒りや怨念を描き出した。対象がとりついてしまって梅原猛は梅原猛でなくなってしまう。まさしくハイデッガー的に言うならば、存在者を超えた存在がそこに立ち現れてくるのである。だから命を削りながら、同時に歴史を越えて根源的な怨霊となった生命が梅原猛を賦活するのである。彼は命を削りながら、根源的な命によって甦らされるのだ。
だから、九十歳を超えた哲学書を書くという梅原のパフォーマンスは、根源の生命に戻り、死して甦ろうとする試みなのであろう。その意味で安易に書き始めれば命取りになるから九十歳を超えて書くというのは賢明でもある。
しかしそれは前人未踏の事だ、まだ人間で九十歳を超えて本格的な哲学書を書いた人はいない。人間の限界への命がけの挑戦なのである。彼はそれで没落してもツァラトゥストラのごとく本望であろう。見事に書き上げれば、根源の生命によって賦活され百歳を超えて生きるに違いない、そんな気さえしてくる。
そんなことになったら彼よりちょうど二十歳若い私は、先に逝ってしまうことになりそうである。梅原猛の生き様を手本に自らを「火の鳥」のパトスで根源の生命の火口に身を躍らせる勇気が欲しいものである。