やすいゆたか
労働本質論は棄てられたのか
 本質は内に住みたる抽象か、関わりの中現見据えよ
本質は内に住みたる抽象か、関わりの中現見据えよ
今日はマルクス入門ということでやさしくカール・マルクス(Karl
Heinrich Marx,
1818年5月5日
-
1883年3月14日)を人間観を中心に話していくことにします。まずマルクスは人間の本質を何と捉えていたでしょうか。
彼は労働者階級の解放を目指していました。働くものが幸せになれる社会を目指していたわけです。逆に言えば、自分は生産に従事しないで、労働者の生み出した価値を搾取してている資本家階級をなくすことによって、搾取のない平等な社会を目指していたのです。
ですから労働するということが最も大切で尊い事だと考えていましたので、人間の人間たるゆえんを「労働」に求めていたということですね。彼と義兄弟みたいな関係だったフリードリッヒ・エンゲルスは『猿が人間になるについての労働の役割』という論文を著して、労働することによって人間ができたと労働本質論を強調したのです。
ただ、エンゲルスの議論には疑問点がありますね。労働が人間の本質で、猿がまだ労働していないとしますと、その猿が労働するわけがないので、人間になったのは労働が原因だといえないはずです。もっともこれは労働をどう定義するかということでもありますが。
たしかにマルクスも『経済学・哲学草稿』(一八四四年)の段階では労働を類的本質だとしていたのです。『資本論』(一八六七年)などの経済学的著作でも労働価値説ですから労働が経済的価値を生み出したとしていることは確かですね。でもこれは商品の本質ですから、マルクスは商品が人間であるという立場じゃないので、ちょっとずれています。まあ『資本論』は資本主義経済の原理を研究したもので、人間の本質を論じるのをテーマに掲げているのではありませんからね。
それで問題になるのですが、『経哲草稿』の翌年に書いた『フォイエルバッハ・テーゼ』(一八四五年)の「フォイエルバッハは宗教的本質を人間的本質に解消する。しかし、人間的本質は個々の個人に内住する抽象物ではない。現実的には、社会的諸関係のアンサンブル(総和)である」という命題です。これは人間の本質は労働ではないということを意味しないのでしょうか。実際この規定を「アンサンブル規定」というのですか、この規定によってマルクスは人間の本質を労働と捉える立場から脱却して、「社会的諸関係のアンサンブル(総和)」であると捉える立場に変化したと解釈しているマルクス研究者が多いわけです。その代表格が田畑稔『マルクスと哲学』です。
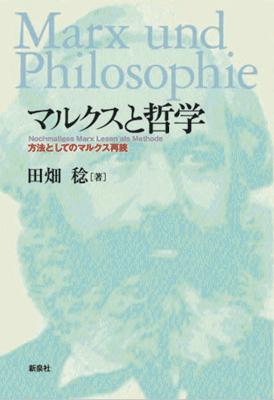

田畑稔
田畑さんによると、「哲学者たち」は、人間の本質を個別存在に内住する抽象として把握してしまって、「現実に実存する、活動している人間たち」「彼らの所与の社会的諸関係」「彼らの現前の生活諸条件」などに対する根本関心がどうしようもなく欠落してしまうと、マルクスは指摘しているそうです。
マルクスもそれまでは、哲学を実現する立場に立っていました。労働のあるべき姿を説いてそれが疎外されているということで、労働者の悲惨な状態を暴いていたわけです。それが急転直下、「哲学」批判を言い出したように解釈されているのですが、哲学的理念で外から批判するだけでなく、現実の諸関係に内在してそこから具体的に変革の論理を導き出すべきだということですかね。
人間は労働によって自己の能力を発揮し、生産物として実現するわけです。この「労働」する能力を人間ならだれでも持っているという意味では、労働という本質が「内住」しているという捉え方も可能です。でも現実的には、だれもが労働するわけではありません。また労働者階級はまだ労働力のほんの一部でした。
具体的には多様な立場と種類の労働があったわけで、現実の社会関係からどのような社会変革の構想が立てられるか考えなければならないのです。あるべき労働の姿から社会を批判しても高踏的で空振りの批判に終わってしまいます。ですから「人間の本質は個々人に内住する抽象物ではない」としたわけです。それで「現実的には社会的諸関係のアンサンブル」なのですが、だからといって、このようなマルクスの表現が、労働本質論の否定になっていると捉えるのはとんでもない誤解ではないでしょうか。
田畑さんたちは、当時のマルクスは、哲学はどうしても、個々の具体的な事物は理念を宿したものとして、その理念を実現すべきものとして捉える学問になってしまうと見抜いたというのでしょう。たとえば現実の様々な社会矛盾からの人間の解放を問題にする場合、人間の本質とは何か、それは理性であり、労働であり。類的共同性であるとすると、現実の人間は、非理性的であり、労働が疎外されており、抑圧と搾取に喘いでいますね。その人間たちを、哲学は、非本質的、非本来的な理念にはずれたものとして高踏的に批判して終わってしまうのじゃないか。そういう「哲学」的良心は清算すべきだとマルクスは捉えていると解釈されているのです。
しかし私の立場は、人間の本質は理性であり、労働であり、社会的存在であり、言語使用であり、その他でもあるという考えですので、本質をどれか一つに絞る必要は全く認めません。ですから、マルクスがその中で社会的諸関係のアンサンブルというのを指摘したからといって、労働本質論が否定されたとは感じないわけです。
ただし、マルクスは「個々人に内住する抽象物ではない」と言っていますね、だから「理性」「労働」「言語」などの抽象的な規定は、人間の本質規定としては、マルクスは択らないとも解釈できるわけです。
でもそれも解釈次第ですね。「理性」も「労働」も「言語」も現実的な社会関係の中ではじめて成立し、機能するのですから、「個々人に内住する抽象物」などではないのです。ですからマルクスが批判したヘーゲル左派の人たちはどうも「個々人に内住する抽象物」として人間の本質を見なしているとマルクスは感じたということです。現実的な社会的諸関係の中で、理性や労働や言語を問題にすべきであるという捉え方をマルクスはしていたと解釈することもできる筈です。それにマルクスは人間の本質を労働や社会的諸関係の総和に見出したことはたしかですが、理性や言語やその他が人間の本質ではないという言い方をしたことがあるでしょうか、私の記憶ではありません。何が人間の本質かは、人間を問題にするそれぞれの領域で当然異なってくると思われます。
では理性が本質だという場面はどうでしょうか?プラトンは魂の三分説で、頭に入った魂である理性と胸の魂である気概、腹の魂である欲望のうち、最も人間が卓越しているのは智恵を発揮する理性だとしました。理性が頭にあるというのはともかくとして、もちろん人間は智恵が他の動物に比べて圧倒的に発達しているので理性本質説は当然です。
労働が本質だというのは、生産活動において人間は労働によって生産物を生み出して自己を生産物として実現することで特色を発揮しています。仲間のコミュニケーションの手段として、人間は言語を遣う事に特色があるので言語本質論も成立します。
これらの本質論を違う場面で使うと混乱します。たとえば生産の場面で人間の本質を問題にする時、生産には理性も言語も必要だからといって、労働ではなく、理性や言語を人間の本質だと言い張っても生産的ではありません。コミュニケーション場面で、労働によってコミュニケーションが発達したから労働が本質だと言い張って混乱させても顰蹙をかうだけです。
マルクスやエンゲルスが労働者の階級的立場を強調したことから、人間の本質を労働に求める人間観を賞揚したことは大いに考えられますが、それを理性を本質とみなす人間観に対抗する人間観だと見なしていたとするのは後世の人の誤解なのです。
疎外論の払拭について
 疎外論あるべき姿論じたり、歴史は生のせめぎあいかな
疎外論あるべき姿論じたり、歴史は生のせめぎあいかな
マルクスは、ヘーゲルの自己疎外の論理を労働の論理として受け止めて、「疎外された労働」の論理を構築しました。ですからその疎外論が払拭されたとしますと、そのことによって、人間の本質を労働と捉える論理も払拭されたと廣松は解釈したのでしょう。
私は「青春の甘きすっぱき疎外論いちど棄てたがまた拾いきぬ」と詠っています。一時は廣松の切断説を採用したのですけれど、経済学批判期つまり『経済学批判要綱』『経済学批判』『剰余価値学説史』『資本論』などの疎外概念の使用例を表示していきますと、後期マルクスに疎外論は生きていることはっきりしました。


廣松 渉 ルイ・アルチュセール
つまり経済学的な原理を問題にすれば当然、生産・流通・消費の仕組みが問題になりますが、基底的には労働生産物が交換される原理をはっきりさせなければならないわけで、労働価値説に内在して行うしかなかったわけです。その際、労働者の立場に視点を置くとどうしても、労働生産物が労働者のものとならず、労働者に外的なものとして敵対してくる疎外や、資本家による剰余価値の搾取が問題にならざるを得ないわけです。
一方、唯物史観によって歴史的展望を切り拓こうという問題意識からは、あるべき労働の理念から現実を批判することより、むしろ歴史的現実に内在した社会的諸関係の分析がより重要な課題だったのです。それで「疎外」というタームにお呼びがかからなくなった。その変化があまりに掌を返したように激しかったので、「疎外論の払拭」という印象が強すぎたのです。
疎外論の払拭という議論は、実は唯物史観の成立の問題でもあります。つまり『ドイチェ・イデオロギー』で唯物史観が確立したのですが、その際に「疎外」という用語が使われなくなったのです。それでマルクスがこの時点でヘーゲル的な観念論から脱皮して、弁証法的唯物論を樹立したのではないか、マルクスがやっとマルクス主義者に成長したという解釈が、スターリン時代からあったのです。その観点からは若きマルクスの労働疎外論は、ヘーゲル的な観念論影響が色濃く残っていたということになります。
たしかに労働は、主体の側の理念を生産物に対象化して実現するわけですが、それが現実の生産物になってしまって、主体から離れると独立して外的なものとして立ちはだかります。それで経済的諸関係が外的な機構としてできあがって、抑圧的に主体を圧倒するわけで、これが疎外ですね。それで生産物の本質が労働であること、自己自身の姿だと認識して自己のものに取り戻さなければならないということになります。こうした論理はヘーゲル的な自己疎外の観念論そのものとも解釈できます。
この観念論というだけで克服された発想だと決めつけられてしまうのはどうでしょう。唯物論を選択するか、観念論を選択するかが、哲学の根本問題だといわれていた時代では、唯物史観の確立が、観念論からの脱皮という解釈には一片の疑問の余地もなかったのです。しかし労働が、理念の対象化であるというのは労働の本質ですから、それが観念論であるなら、観念論でもいいわけです。唯物論でなければならないというのは、法や制度やイデオロギーなどの上部構造の土台に経済的諸関係があって、それによって上部構造が規定されていることを忘れてはならないことなどですね。
マルクスは哲学者をやめたという解釈も有力ですが、それならば、学問の方法として首尾一貫して唯物論だけを方法にしていなくてもいいということにもならないでしょうか。つまり労働疎外論では観念論的な捉え方をし、歴史の発展を捉えるのには唯物論的な捉え方をしたということです。一人の思想家の中に取り扱う分野によって観念論的方法と唯物論的方法を振り分けていても不思議はないわけです。
『経済学・哲学草稿』でも唯物論でも観念論でもないという表現があったりして、解釈不能になったりしていたわけですが、廣松渉の登場で既成の弁証法的唯物論が根底的に問い直されたり、冷戦終焉後は社会主義世界体制の崩壊などで唯物史観の図式そのものが破綻したというか、全く信用を失った格好ですよね。その意味では、疎外論が観念論だから克服されたという発想はやめにしようというのは説得力が出てきたようなのです。
ですからマルクスが、観念論だと批判したり、唯物論だと批判したり、哲学的な姿勢を批判したりしていても、それがどういう場面で、どういう問題意識の下で行われているかを見極めないと、それを観念論自体や唯物論自体、哲学自体の否定や克服とみなすのは早計なのです。
労働と疎外
 労働は己の力物にして示したること喜ばしきや
労働は己の力物にして示したること喜ばしきや  対象の中に己を喪したり、働くことは疎外なりしか
対象の中に己を喪したり、働くことは疎外なりしか
労働本質論にはポジティブなタイプとネガティブなタイプがあります。対象に働きかけて、それを変革して獲得するという意味では、自己実現ですから素晴らしい本質なのですが、他方では労働は、そうしなければ生きていけない労苦ですね、これは否定的な本質なのです。『バイブル』では楽園では労働の必要がなかったのです。あたかも子宮の中のようにすべて用意されていたわけです。それが罪に堕ちて、エデンの東に追放されると痩せた土地を一日中働いても働いても貧しい暮らししかできなかった、まるで労役のような人生なのです。明らかに労働は神の罰として意識されていたわけです。
マルクスの労働論も労働を対象変革活動であり、自己対象化、自己実現として捉えるポジティブな面と、生産力の発展によって必要労働時間を減らしていくというネガティブな問題意識の両面があります。では「疎外された労働」というのもネガティブな労働観でしょうか?いや、「疎外された」というのは本質が発現できていないということですから、「労働」は本来自己実現で肯定的なものなのに、疎外されて自己喪失の活動になってしまっているということですから、「疎外された労働」は否定的な労働ですが、労働自体はポジティブに捉えられているわけです。
労働は対象化、外化ですからそれは必然的に自己にあらざるものに自己をしてしまうことになり、疎外を伴わざるをえないとヘーゲルの自己疎外論ではなります。そこがフォイエルバッハの人間学的唯物論の立場を継承しようとするマルクスにとって、ヘーゲルの観念論に対する不満でもあったのです。
つまりヘーゲルの主体は結局自己意識なのです。つまり自己は自己であるという抽象だったのです。ですから意識が自己を外化し、対象化して自己にあらざるものを定立したとき、それは具体的な事物の形をとるわけですが、自己にあらざるものとして主体は疎外を感じます。そこで対象の他在性を否定します。これは本来自己である意識の対象化であった筈で、本質において意識である筈だとして、他在にあって自己にある意識に還元するわけです。つまり対象としての生産物は事物としては主体ではないものでしかないわけですね。
ところが主体をフォイエルバッハやマルクスのように生命的な身体として捉えていますと、労働生産物は自己の身体的能力の対象化であり、身体のうちに獲得された自然として、身体の延長、人間的自然として捉えられるわけですから、対象化はそれ自体では疎外ではないのです。
それでは先ほど言いいましたマルクスの自己疎外論は観念論だという議論と矛盾するように思われそうですね、自己疎外論にも唯物論的な自己疎外論があることにならないかと批判されそうです。そこはダイナミックに捉えていただきたいですね。自己疎外論は理念の対象化、実現という意味であくまで観念論的な構えなのです。労働の自己対象化といいましても、身体的能力の発現ではあっても、対象化(事物化)されるのは理念なのですから。それが主体を唯物論的な自然的身体と捉えることで、人間的自然の立場を基礎づけることもできるわけなのです。
そうすると労働にも二つのタイプがあることになります。必然的に疎外でしかない労働と、それ自体では疎外されないで済むかもしれない労働という。ヘーゲルとは違ってフォイエルバッハやマルクスにとっては労働生産物として自己を対象化すること自体は自己実現であり、自己疎外じゃないのです。もちろん満足の行くように創れない場合は自己疎外になりますが、一般的には疎外ではないのです。むしろ自己が身体の限界を超えて拡張しているわけですね。
他方で商品生産においては、生産物に価値を対象化する場合は必然的に自己疎外になります。価値は生産物の具体的な有用性を捨象し、抽象的な価値に還元することによって見出されるのです。この価値を産む主体は、自己対象化ですからやはり価値なのです。つまりヘーゲルの自己意識に当たるのが商品の本質である価値なのです。
しかし価値は、価値という抽象では自己を示せませんから、具体的な有用物を生み出す具体的有用労働として働いて具体的有用物を生み出すわけです。しかし価値は元々具体性の抽象ですから、具体的有用労働は抽象的人間労働に還元されるための仮の姿でしかないわけです。
マルクスはヘーゲルの自己意識の疎外を抽象的な自己意識の自己対象化として捉え返したのです。つまり抽象的な労働の原理として受け止めていました。それがベースにあって『資本論』の「抽象的人間労働」というターム(用語)が生まれたという解釈をしています。これは私の修士論文『労働概念の考察』のテーマでした。それが最近のヘーゲル研究で分かったことですが、イェナ時代の若きヘーゲルの精神哲学の構想ではすでに「抽象的労働」というターム(用語)が使われているのです。もっともマルクスは読んでませんよ。
ただし労働が必然的に疎外の構造を持つということは、人類的な視点で捉えるとよく分かりますね。文明は人類が生み出した労働生産物ですが、これは人類の自己疎外として現れています。この疎外は必然的なように思われますね。
確かにそれは否定できません。私が労働は自己対象化、自己実現としては本来的には疎外されないものだというのは、あくまでもその限りでありまして、決して現実の社会関係の中では疎外されたものにならざるを得ないことを否定するものではありません。
マルクスは私有財産制のもとで市場経済が展開すれば、必然的に労働の疎外が起きると考えていたようです。文明は財産の集積を前提にしていますから、市場経済の一定の発達に伴っていました。その上で国家権力の収奪や戦争、交易などで富が集積したわけですから、その下で厳しい収奪や酷使に耐えた人民の疲弊があったのです。でもだからといって労働それ自体に疎外があるとなると、疎外された労働を生み出す原因の追求が行えなくなってしまいます。
非有機的身体と人間的自然
 わが心天地の心と一つなり、天地は我の五体に近しや
わが心天地の心と一つなり、天地は我の五体に近しや
『経済学・哲学草稿』では「自然は人間の非有機的身体」という捉え方があります。また「人間的自然」という表現や、「貫徹された自然主義は貫徹された人間主義であり、貫徹された人間主義は貫徹された自然主義である」という表現もあって、こういう表現が人間中心主義なのか、それとも人間中心主義と自然主義の対立を乗り越えるものなのかということが1960年代には公害問題とも関連して大問題だったのです。
「非有機的身体」というのは、身体的な器官としてはつながっていないけれど、器官同様生きていく上で不可欠なものになっているものという意味です。動物のレベルで考えますと、貝の貝殻、蓑虫の蓑、蜘蛛の糸、鳥の巣、狐の罠、ビーバーのダムなどが挙げられます。人間の場合はいまや地球全体を非有機的身体にしているわけです。
その意味では人間概念を自然にまで拡張する試みは『経済学・哲学草稿』で既に試みられているのですね。これには衝撃を受けました。私がマルクス主義の基本文献を読み始めたのは高校生の頃だったのですが、大学生になって『経済学・哲学草稿』に出会い、自然を人間の身体として捉える発想に感銘しました。つまり自然を他者ではなく、自己自身として引き受け、自然の自己意識になろうとしているわけでしょう。これはすごいと思いましたよ。
しかし、本来他者でしかない自然を自己の身体にしてしまうということは、自然を人間中心に捉えて、人間の手段にしてしまうことではないのかとマルクスを批判する人もいます。そういう解釈はマルクスに気の毒ですね。マルクスは「人間は自然の一部」という立場に立っています。そういう意味で自然は人間の身体なのです。ですから、人間の意識は自然の自己意識だというシェリングの発想を継承しているわけです。
ドイツ観念論は、「同一哲学」だと言われます。といいますのが、「存在と意識の同一性」を強調したからです。カントでは現象界に関する限り、認識されたものは感覚を統覚の先天的なカテゴリーで統合したものである、ということは人間は人間の意識内容を存在として認識しているだけだということですね。フィヒテはだから、意志の自己展開として世界を論じました。シェリングは逆に人間の意識こそコスモス自身の意識であり、コスモスの現れだということです。ヘーゲルはこれらを総括して、絶対精神の自己展開として哲学体系を作り上げたわけですね。マルクスもその延長上だということになるのでしょうか。
存在が意識された存在である限りは、観念論に嵌るわけですが、意識が存在についての意識である限りでは、唯物論的です。それでマルクスは『経済学・哲学草稿』で「貫徹された自然主義あるいは人間主義が、観念論とも唯物論とも異なっていること、また同時に、それがこれら両者を統一する真理であるということを我々は見いだす」と述べたのです。つまり同一哲学としてのドイツ観念論は、「存在が意識と同一だ」ということを強調しました。
それに対してフォイエルバッハやマルクスは「意識は存在と同一だ」という面を打ち出したのではないでしょうか。つまり、意識が主体だと言うのに対して自然が主体だという立場です。
ただしそれは、人間主義を否定して自然主義を打ち出すのではないのです。そうではなくて、自然を自己の身体にしているような人間主義を打ち出した。それは人間の意識を自然が取り込んでいるという意味では貫徹された自然主義だけれど、自然を自己の身体にしているという意味では貫徹された人間主義です。これこそ人間と自然の断絶を乗り越えるロマン主義の極致ですね。
しかしそれではまだ「存在と意識の同一」というドイツ観念論の枠内にいるわけになるともいえます。意識の土台や、意識の彼岸としての物質概念には到達していないわけですから、唯物論とは言えないのじゃないという疑問が生じますね。
でもそういう場合の「唯物論」は、「意識から独立した客観的実在」を物質だと捉えるレーニンの『唯物論と経験批判論』の影響があるのではないでしょうか。意識から独立しているのだったら意識には捉えられないわけで、マテリー(質料)と混同されています。実際唯物論はマテリアリスムス(質料主義)と混同されがちです。
『フォイエルバッハ・テーゼ』における実践的唯物論
 対象をただ客体と見るなかれ、吾が実践の姿ならずや
対象をただ客体と見るなかれ、吾が実践の姿ならずや
1845年に『ドイチェ・イデオロギー』のための覚書として書かれたのが『フォイエルバッハ・テーゼ』です。この『テーゼ』で疎外論は払拭されているとアルチュセールや廣松渉は強調しています。ここでフォイエルバッハを批判しているので、人間学的唯物論を脱却して、弁証法的唯物論を確立したというのが旧来の解釈だったわけです。でものっけから次のようなすごい内容だったのです。
「これまであったあらゆる唯物論、それにはフォイエルバッハのものも含まれます。その主要な欠点は、対象(事物)や現実や感性が客体あるいは直観という形式のもとでしか捉えられていなかったことです。つまり感性的人間的活動、すなわち実践として、主体的には捉えられていないということです。」
対象というのは、客体であり、事物であるわけです。Gegenstandは対して立つだから客体的な事物なのです。しかしそういう捉え方だけだと駄目だということですね。主体的に自分の実践の姿として捉え返さないと駄目だということです。つまり自分とっての他者として客体的事物として物事をとらえていたのでは、対象は自分の存在とは別物になってしまい、それと関わることはできないということです。自分自身の実践の姿として事物を捉え返すことで、対象が自分自身の感性的活動になるのであり、自分自身として捉えられるのだという事です。
たとえば最近ハリケーンや台風が強風化して甚大な被害が出ていますね、その原因は地球の温暖化ではないかといわれています。それは近代の産業革命以来の工業化によってもたらされた現象ですから、我々の日々の実践の帰結でもあるわけです。ですからたんなる自然現象として手をこまねている場合ではなく、自分自身の現実として主体的に受け止め、自分自身の生活のありかたを問い直し、改革していかなければならないわけです。
感性だって自分のものと感じられないとはどういうことでしょう。それは美しいものを見て美しいと感じたり、醜いものには目を背けたり、あるいは腹立つこととか、喜怒哀楽を感じることがいっぱいありますね。そう感じている自分がいるわけですね。そう感じられる世界があるわけでしょう。それが自分自身の生きてる姿、実践のありようなのです。そう主体的にうけとめないで、他人事みたいに批評ばかりしている、解釈をしたり、自分とは関わりないたんなる経験で終わってしまっているわけです。マルクスはそう感じられる自分、自分の世界を、主体的実践として捉え返そうという構えなのです。これって本居宣長の「物のあはれを知る」というセンスに近いですよね。
この文章から実践を存在の根底として捉える実践的唯物論だという評価が1970年代の東ドイツでなされたのです。そしてこれこそがマルクスの唯物論の本来の姿だとして、マルクスの唯物論を実践的唯物論として表現する人もでてきました。しかし実践が事物よりも根底にあるとすれば、唯物論というよりも実践論になってしまいますね。ですから唯物論にこだわる人は、身体的諸個人や自然的社会的諸事物の対象的関係を前提に実践を捉えていたのです。
しかしこれも従来の唯物論や哲学の観照的態度を批判したまでのことでして、その限りで存在の根底に実践を見たわけです。逆に実践の構造を捉え返そうとすれば、事物の対象的な関係を根底に捉え返す必要があるでしょう。一つの命題にマルクスの哲学や立場をすべて還元してしまいますと、既成のマルクス像を覆すことはできましても、マルクスの他の命題と矛盾してしまうことが多々あります。
つまりこの時期のマルクスは、青年ヘーゲル派を『ドイチェ・イデオロギー』で乗り越えようとしていたわけです。彼らの特徴は、それぞれ個性的な人間観、歴史観、社会観で現実を批判し、裁断することで、新しい時代を切り開けると思い込んでいるところにあるとマルクスは評価していました。それはとんでもない転倒した思い上がりだというのです。
マルクスたちは経済を土台にした生活の実践の中で物事に対する認識の仕方が形成されるので、勝手に意識革命を唱えて、それで社会や時代が変えられるものではないのです。土台になっている生産様式や生産関係がどうなっていて、そこからどんな矛盾が生じ、生産力の発展に伴ってどういう問題が解決が迫られているのかということを認識しなければなりません。その上でそういう課題を解決できる思想を構築すれば、社会変革ができるわけです。
青年ヘーゲル派の面々も自由を求め、封建的なドイツの変革を目指して論陣を張っていたのです。ですからマルクスに解釈ばかりしている哲学屋みたいに批評されるのは心外だったでしょうね。しかしマルクスに言わせれば、バウワーの「自己意識」にしても、シュティルナーの「唯一者」にしてもフォイエルバッハの「人間」にしても、現実の資本主義社会の矛盾から自己を解放せざるを得ない変革主体ではありませんから、結局高踏的に社会の外から様々に解釈して批判を投げかけるだけなのです。
要するにプロレタリアートつまり労働者階級という変革主体を見出していない限り、ドイチェ・イデオロギーは空振りなんだということですね。ですから第十一テーゼの「哲学者たちは世界を単にさまざまに解釈しただけです。肝心なのは世界を変革することなのです。」もそういう文脈で解釈すべきです。
ただし彼は変革主体としての労働者階級を見出したことによって、かえって人間観を限定してしまうことになってしまいました。彼は、主体としての人間を現実的諸個人としての労働者階級に限定して捉えます。その際、人間の非有機的身体としての道具や機械などを含んだ人間的自然を主体として捉えるという『経済学・哲学草稿』の人間的自然は後景に退いてしまうのです。
『資本論』における価値ガレルテ論
 労働が膠になりてとりついて物を価値だと誤たせしとは
労働が膠になりてとりついて物を価値だと誤たせしとは
『経済学・哲学草稿』では人間的自然や非有機的身体として社会的諸事物や人間環境を構成する自然が、人間の定在に含まれて捉えられていたとも解釈できるのですが、他方でマルクスにはそれと矛盾する捉え方もあるように思われます。それは社会関係を身体的な諸個人の関係として捉えようとする見方です。つまり、社会的諸個人や環境的自然も含めて社会的関係を捉え返そうとすると、それは人間関係を物と物の関係に置き換えているのだという批判がマルクスから戻ってくるわけです。いわゆる物象化論やフェティシズム批判論ですね。
これは『資本論』で本格的に展開されているわけですが、労働価値説と不可分の形で主張されています。つまり商品の本質は価値ですね。この価値は事物に対象化され、事物の価値支配力となった労働が実体です。この労働は既に事物になっているわけです。
ところがマルクスは、価値実体としての労働は事物の属性ではないというのです。それは抽象的人間労働のガレルテ(膠質物)だと主張します。具体的有用労働なら具体的な活動ですから、具体的有用物の姿になって対象化されます。効用は事物の属性と考えてもよいのです。しかし抽象的な労働は具体性を捨象してしまいますから、事物には成り得ないというのです。
ですから抽象的人間労働それ自体のかたまりとして労働生産物に付着しているというわけです。それで膠なので付着する膠質物という表現がぴったりくるのです。こうしておけば価値関係は事物に付着している抽象的人間労働の固まり同士の関係であり、人間関係に他ならないというわけです。
それで商品関係は労働生産物の関係のように見えるけれども、人間労働同士の関係であり、現実的な諸個人間の関係に他ならないというわけです。それを価値関係とすることで、あたかも価値が付着している労働生産物の関係であるかに置き換えられているのだという理屈です。この価値つきもの説は、私の独特の解釈で、ほとんど知られていないのです。
フェティシズムというのは、元々は例えば蛇とか石とかを神として崇拝するわけです。それを経済に置き換えますと、品物を価値と見なしたり、紙切れや金属片を貨幣つまり一般的等価形態とみなすわけです。そういう人間でない事物を崇拝するので、マルクスは倒錯だといったわけです。
マルクスは事物やその効用が価値なのではなく、抽象的人間労働の固まったもの、つまり膠質物(ガレルテ)が価値だと定義しているわけです。ですから典型的な労働価値説ですね。それを極端に純化しているのです。廣松渉は、投下労働価値説はマルクス自身の説ではなくて、「叙述の便法」だとしていますが、それはマルクスが言ったことではないのです。廣松さんの解釈にすぎないわけです。
マルクスが自己疎外論を払拭し、主客図式を超克しているとしたら、おそらくマルクスは労働が投下され固まって価値になるという、主観・客観を前提した捉え方にはならなかったはずだという廣松さんの立場にひきつけた我田引水なのです。『資本論』でも口先で唱えるように読んでいてはマルクスの真意は分かりません。ですから廣松渉みたいな鬼才が現れて、廣松的な「マルクスの哲学」に基づいて解釈されてしまうと、ひょっとしたら『資本論』はスミスやリカードの労働価値説を批判的に継承したのではなくて、乗り越えたのではないかとコロッと思ってしまう人が多いのです。
価値が抽象的人間労働の固まりだというのは私も異議はないのです。ただじゃあ抽象的人間労働の固まりである価値は、労働生産物の属性ではないのかということですね。マルクスは価値を労働生産物の属性とは捉えていないわけです。もし労働生産物の属性として価値を捉えているのだったら、価値は労働生産物の性格ですから、労働生産物を価値物と見なしていいわけです。すると事物を価値と捉えるフェティシズムだということにはならないでしょう。
事物が価値を属性としているから、それを崇拝するのがフェティシズムだとマルクスは捉えているのではないのです。マルクスはフェティシズムを倒錯だと批判しているのです。超越神信仰の立場にたっている人々にとっては、蛇や石を神として崇拝している人々は、とんでもない倒錯に陥っているわけでしょう。蛇や石ころが人間たちの願いを叶えるオカルト的能力を持つはずがないと考えています。フェティシズムは最も幼稚な迷信だと思われているのです。マルクスがこの未開人の宗教が資本主義社会では最も普遍的な信仰になっていて、その倒錯の上に経済が成り立っていると批判しているわけです。
ということは、マルクスの考えでは、労働生産物は価値を属性として持っていないにもかかわらず、それ自体が価値だと思われているというわけです。でも実際にマルクスは抽象的人間労働によって労働生産物が作られているとしているのです。労働は具体的有用労働だけではなく、抽象的人間労働でもあるという二重性をもっているのですから。
同じ労働の二面性だから、それは作り出した労働生産物の二面性になるという解釈も可能ですね。労働生産物が効用(使用価値)と価値という二面を持つと考えれば。ところがマルクスは労働生産物と商品を区別しています。商品の本質は価値だけれど、労働生産物の本質は価値ではありません。マルクスの考えでは労働生産物に価値は属していないのです。
マルクスが必死になって労働の二重性を強調したのは、それによって形成されるものは別のものであって、両者を混同するのは倒錯だという意味なのです。
具体的有用労働が使用価値を形成し、抽象的人間労働が価値を形成するので、使用価値も価値も両方とも労働生産物に属するように思えますね。ところが、価値というのは労働生産物の価値だと見えるのは倒錯だとマルクスは言いたかったのです。マルクスの価値の定義は、「価値は抽象的人間労働のガレルテ(膠質物)である」というものです。このガレルテは「凝結」とか「凝固」とか訳されています。つまり抽象的人間労働の固まりが価値だという意味ですね。ところがその固まりとは労働生産物のことではないのです。
マルクスは労働生産物という物の方に価値があるのではなく、労働に価値があるという立場なのです。それで物に価値を属させる見方は倒錯だというのです。マルクスによれば、抽象的人間労働の固まりとしての価値は、マルクス自身の表現では「価値は抽象的人間労働のガレルテ」だとしているのです。抽象的人間労働は投下凝結されているわけです。ただし、投下凝結されても労働生産物になるのではなく、抽象的人間労働それ自身の固まりになっていて、膠としてくっ付いているというのです。ですからガレルテ(膠質物)は、無造作に「凝結」や「凝固」と訳してはだめなのです。フェティシズム批判が抜けてしまう懼れがありますから。
マルクスの言い方だと、抽象的人間労働自体が固まって労働生産物にくっ付いている憑き物が価値だということになります。しかしそんなのどこにもないじゃないか、ということで、むしろ廣松流に解釈した方が合理的だという見解もありえます。つまり価値は労働の社会関係であって、マルクスは必要労働時間が労働生産物に価値性格を与える経済関係の仕組みを、あたかも抽象的人間労働の固まりが憑き物のようにくっ付くかにレトリックとして表現したという解釈です。そのレトリックを本気のように受け取っている保井温(やすいゆたか)は大人気ないじゃないかというのです。
マルクスは価値を憑き物として見なしていると解釈すると、マルクスはフェティシズムを批判するあまり憑き物信仰に陥ったということになってしまいますね。それはあまりに乱暴な解釈じゃないか、暴論だとマルクス研究者の中にはあきれ果てる人がいるわけです。
実際、私も笑いましたよ。レトリックだと思いました。でも本当にレトリックかどうか、マルクスのような科学的に思考をする人は憑き物信仰には絶対に陥らないのか、それ自体面白いテーマですね、まさかそんな筈がないということで調べなかったら、学問的には大きな獲物を取り逃がすことになるわけです。
私がいわゆるマルクス主義者だと自覚していて、マルクス批判はしたくないというような抑圧が潜在意識に働いていれば別ですが、生憎私は自分をマルクス主義者だと思ったことはなかったのです。
それで『資本論』の中でフェティシズム論がどのように貫いているのか、価値は憑き物として展開されていないかどうかを注意深く読み込んでいったのです。そうすると価値=憑き物というのがあながちレトリックではなく、本気だということが分かったのです。いちいち展開すると膨大になりますが、価値が原材料や機械から製品に移転するという表現などはその典型です。
それもレトリックだという可能性があると反論されるでしょうが、それなら『人間観の転換―マルクス物神性論批判―』(青弓社一九八五年刊、ホームページに『資本論の人間観の限界』と改題して掲載)で『資本論』全巻について展開していますから、じっくりお読みいただくしかないですね。実際だれも本格的に私の著作を批判している人はいません。
では一応価値が抽象的人間労働それ自体の固まりで、労働生産物に付着しているとマルクスが考えていたことにします。そうしますとどうして労働生産物が価値であるかに倒錯されるのでしょうか。それは次のような論理からです。
具体的有用労働ですとその成果は具体的な有用物になりますが、抽象的人間労働ですと労働が継続したという事実だけですから、具体的な物にはなりえません。ですからそのガレルテは具体性がなく無色透明です。ですからそれは膠ですので、くっつくのですが、たとえくっついていても見えないわけです。それで価値は労働生産物の属性であると誤解されてしまうのだとマルクスは考えたのです。
マルクスの考えでは、商品は商品経済の中でだけ商品なので、労働生産物それ自体は商品ではないと考えるのです。衣服や食糧は商品経済の発生する以前から存在したし、将来の共同体で商品経済がなくなってからも存在しています。ですから商品経済で一時的に価値を持ったように見えても、それは社会関係からそのように見えているだけで、労働生産物それ自体は何も変りがないのだから、価値を含む筈がないというわけです。
私は無理に価値を憑き物にように捉えなくても、商品生産で作られた労働生産物には、商品社会を構成しているわけですから、他の商品に対する支配力としての価値性格を認めてもいいと思うのです。その場合に商品生産発生以前とか、商品生産止揚以後の労働生産物とは効用面では同じでも、商品として活躍する分は違うわけですから。
効用としては衣服であり米であり全く同じです。でもその衣服は商品として作られたのなら、商品としての働きを流通や消費面でするわけです。でもマルクスは抽象的人間労働の固まりが労働生産物とりついているからそう見えるだけで、価値の実体は抽象的人間労働なのだから、あくまでも価値は人間の社会関係だというわけなのです。
『資本論』の人間観の限界
 雇われて働く者のみ価値を生む、一点張りでは視界狭めり
雇われて働く者のみ価値を生む、一点張りでは視界狭めり
 人間は身体のみの存在か物の中にぞ己見出す
人間は身体のみの存在か物の中にぞ己見出す
では価値ガレルテ論から帰結する『資本論』の人間観の限界というのはどういうことなのでしょうか。
『資本論』の最大のテーマは剰余価値理論を確立するところにありますね。つまり労働者の労働がすべての価値を生むのであり、そこから労働力の再生産費を差し引いた剰余価値が利潤の源泉で、それが資本に転化するという論理があります。これに対して、資本家の利得を正当化する経済学からは、資本家が所有する生産手段や資金などの役割を強調し、資本家の利潤獲得を擁護しようとするわけです。そこでマルクスは生産手段がいかに生産に大きな役割をしているとしても。それは手段でしかなく、生産の主体は労働者であること、そして価値はあくまで労働者の労働だけが生み出していて、機械や原材料は働いていないことを強調します。
マルクスは価値を労働者の抽象的人間労働のガレルテと定義してしまいました。それを前提として展開するので、ところどころで無理が生じます。でも彼は、それをフェティシズム論で強引に突破していきます。たとえば生産は労働者だけでなく生産手段も一緒になって働いて行われ、生産物ができますが、その主体は労働力だけであって機械は手段だから働いていないことになり、当然価値生産には加わっていないことになります。でもちゃっかり生産手段の価値は生産物に移っているのですね。その分も労働者の労働がしたことにしなければならないわけで、これが具体的有用労働による価値移転論です。
生産組織や機械の改良による飛び抜けた生産性の獲得は、特別剰余価値をもたらしますが、その際に労働者の労働自体はかえって単純化していて,とても労働者が特別剰余価値を生み出したとはいえないのですが、マルクスは最新の機械が普及するまでの間、技術革新によって労働者の労働が強められて特別剰余価値を生み出したのだとするのです。
マルクスは定義的に生産主体や労働主体は、労働者でしかありえないという大前提をおいて、機械は単なる手段という立場で展開しますから、生産手段が自己の価値を生産過程で生産物に対象化するという活動を評価できません。そんなことをすると物が労働することになるので擬人化であり、フェティシズムになってしまうからです。
道具と機械の違いを考えてみると理解しやすくなると思います。道具は人間の身体の延長という捉え方で説明しやすいのですが、機械となると立場は逆転します。むしろ人間身体は機械の部品となって、機械が自動的にこなせない作業を補完しているのです。ですから特に労働者の作業が特別に主体的ではありません。むしろ機械的に作業をこなさなければならないのです。生産主体は企業全体であると言えるでしょう。そこでは個人単位の人間観では対応できないのです。逆に言えば労働者の個人的な身体は、小型の多機能自動機械となっており、その維持・再生産費が賃金です。もちろんそれは人格を備えていますので、人格に対するさまざまな配慮が必要になりますが。
ということは機械制大工業の時代では、機械が生産の主力になっており、その機械がまだ不完全な部分を人間身体が機械部品あるいは多機能小型自動機械として補完しているだけで、最終的には完全自動化の無人工場になっていくということですね。そうしますと、身体的個人としての人間でなく、機械も含めた企業全体としての人間という捉え方も必要だということです。そこまでいくと未来論みたいで、まだ現実論としてはピンとこないかもしれませんが。そういう事も考えておく必要はある時代に入りつつありますね。
マルクスは機械の圧倒的な意義を捉えているのですが、それで特別剰余価値の生産を最新鋭の機械が行っているように見えることを強調していますが、それでも機械が価値を産むことはあり得ないという立場に固執するので、機械によって「強められた労働」つまり労働者の労働が特別剰余価値を生んだとしているのです。
それは機械を含めて人間を捉えない限界からきているので、機械も含めて人間と考えれば、特別剰余価値を機械が生み出したことになるわけですね。としますと、労働者だけではなく生産手段も労働しているという論理になり、剰余価値だって、労働者から搾取しているとは限らなくなりませね。搾取理論が崩壊するじゃないかといわれそうです。
マルクスは可変資本(労働力)と不変資本(生産手段)という区別を立てて、可変資本である労働力からだけ剰余価値が生み出される仕組みを明らかにしたのです。不変資本は原則的には剰余価値を生みません。例えば一億円の機械は、一億二千万円の価値を生み出して償却されるとしますと、一億二千万円でも売れるわけですから、市場全体を考えますと、平均的には剰余価値を生み出すことはないわけです。特別剰余価値を生む場合には別ですが。
それに対して可変資本はその再生産費が賃金として支払われますが、その分しか価値を生まなければ剰余価値がでませんので、資本家は利潤をえることができません。それで原則的には賃金以上に価値を生み出して剰余価値を資本家にもたらす労働力のみを雇用することになります。それで可変資本だけが剰余価値を生むということになります。
生産手段も価値を生むとしても不変資本の場合は、自己の価値分と等量の価値を生産物に対象化することになり、そこには平均的には搾取は起こりません。やはり労働者の労働から搾取するという理論は有効です。ただし技術革新によって機械の働きから特別剰余価値を獲得することができるわけです。そして市場の平均より安く買って、より多くの価値を機械が対象化するような工夫をすることで剰余価値が生まれるわけです。
労働力の場合は相手は人格であり、支配下において必要労働時間以上に働かせて、剰余価値を搾り取ったわけですね。物の場合は搾取されているという感覚はありませんが、労働者の場合は労働を強化させられたり、労働時間を延長させられたりして苦痛を伴っていますよね。人と物を混同するのは酷いのじゃないか糾弾されそうですね。
しかし今は経済学的な地平で語っているわけでして、経営学上の労務管理の水準ではありません。剰余価値が生み出されるかどうかで人格や感情を登場させる必要はまったくないわけです。人と物の区別も経済学においてはむしろ止揚されるべきではないかということなのです。経営学ではそうはいかないのは承知しているつもりです。梅本克巳は、人間は商品という物ではあり得ないのに、資本制生産では労働力商品として物化、商品化されてしまうという矛盾を問題にしました。この物化・商品化を拒否しようとするところに主体性を求めるわけです。
人間の本質を問う場合に、他の動物に対してどのような能力が秀でているかを問題にすれば、答えは理性的能力ということになります。もちろん主体性や実践に人間の特色を求めるのもいいでしょう。しかし経済活動の構造的認識が問われている場面では、人間は物と物との関係を通して社会を形成し、物として自己を認めさせなければならないのです。物化や商品化を非人間化としてそれらに包摂されることを避けていますと、社会の中で生活できなくなります。
でも労働という概念は、主体が予め思い描いているものを目的意識的に作り出すという内容をもっています。ところが生産手段だと、意識的に活動しているとはいえないので、生産手段も労働するなんて全く的外れな滅茶苦茶な議論だと言われます。
でも良く考えてください。道具の場合、手の延長として捉えられますね。すると労働する主体としての人間には道具も含まれているわけです。主体を意識だけに限定せずに、働きかける人間としますと、それは身体およびその延長としての道具を含みます。それを労働しているのは身体だけで、道具は意識しないから労働しないとはいえないわけです。たしかに身体と道具を分けましてどちらが人間かと問われますと身体だと答えます。でも生産の場で労働する場合は、そのような身体と道具を分けてどちらが人間かを問うのは間違いです。道具があって初めて働けるわけですから。
機械制大工業のもとでの労働は、機械が主力で労働者の作業はその補助として機能する場合が多いわけです。それを機械の分は人間ではないからといって差し引くわけにもいきませんし、機械を動かしているのは労働者の作業だと強く主張するわけにもいきません。機械だって人間が作ったのだし、機械を動かすのも人間だとだから機械は働く主体じゃないと反論されますね。でも機械制大工業では、人間に機械を含めることによって、人間が生産主体であると言えるわけです。つまり労働者個人の身体と機械を包摂した機構としての企業システムが、機械の機能や労働者の作業を統括して生産主体として仕切っているのです。その中で労働者の労働も機械の作業も生産物とその価値を形成する協働を行っていると言えます。
でも機械には意識がないから労働しているとはいえないと頑張る人もいます。でもね機械には工程がインプットされています。原材料をプログラム通りに変化させ変形し、組み合わせて予め予定されていた目的通りに製品化するわけですから、装置の中に思想や概念が物質化しているとも言えます。反対に労働力がどれだけ目的意識的かよりも、自動機械としてプログラムを効率的に遂行できたかどうかが問われます。その意味では、いずれは自動機械に取り替えられるべき存在なのです。ともかく全体として人間の意志や目的のもとに統合されて対象を変革しているのですから、労働力だけの活動や生産手段だけの活動を切り離してどちらが人間かを問うのはナンセンスなのです。
しかし私が機械や生産物をも含めて人間だと言いますと、個々の機械や生産物もそれぞれ人間だといわれているような気がして納得がいかないという人が多いようです。でもそれは身体的諸個人でも同じ事です。ただ孤立していれば人間しての本質は発揮できません。狼に育てられたアマラとカマラが人間社会に戻されてもなかなか人間になれなかったようなものです。個々の社会的事物が人間に含まれるのは、それが効用や価値存在として、個人や他の事物との間で社会関係を構成することにおいてです。
じゃあ、上着とか携帯電話だとかカレーライスが人間なのか、そうなると人間じゃないものを人間だと言っているようなものだということになります。そりゃあそうですね、つまり人間観を転換しているのです。ですから既成の人間観にこだわっている限り、わたしの議論は納得できなくて当然なのです。
人間社会は人間的環境と社会的諸事物と身体的諸個人が生産―流通―消費の循環を形成しているわけです。その限りでそれぞれの事物が存在できているわけですから、携帯電話が存在できるというのも、人間的効用して認められ商品価値を持つからです。そういう人間的規定を本質としてはじめて存在できるという意味で、携帯電話も人間の定在だと言えるというのが私の「カテゴリーとしての人間」論です。
私の人間論の展開はひとまず措くとして、マルクスの『資本論』では、社会的諸事物が商品として社会関係を取り結んだり、生産で価値を形成しても、それらを人間でないから「机が踊りだす」とか言って倒錯と決めてかかっているわけです。そこで人間観を転換して経済社会においては人間環境も社会的諸事物も身体的諸個人も人間的自然を構成し、経済循環を形成しているので人間の定在として捉え返すべきだというのが私の提案なのです。
それは初期マルクスの人間的自然の立場、「貫徹された自然主義は貫徹された人間主義であり、貫徹された人間主義は貫徹された自然主義である」という立場を発展させることになったのにということなのです。